観終わって感じたこと
最初から最後まで一貫して感じたことは
これは、「動く絵画」「動く絵画の美術展」だなと思いましたね。
スウェーデンの奇才ロイ・アンダーソン監督の美術展だなって。

映像もなんとなくスウェーデンの画家が描きそうな色調(クールでシルバーグレー)で(※個人的偏見です。)
常に寂しそうで、モノトーン、音が少なめ、全体的にスロー。
でも映像自体は美しい。
印象を大切に残してほしい。 そんな映画です。
今の若い人達は、早回しで映画を観るそうですが、
この映画は早回しで観ると台無しになるので、逆に観ない方がいい、そんな映画だと思います。
こんな映画でした
この映画は33シーンに分かれていて
それぞれ、ワンシーンワンカットで撮られています。
ですから、カメラが動くことはなく、中の登場人物がそのカメラ枠内だけで動くという。
だから、余計に絵画的に見えるのだと思います。
「さよなら、人類」などで知られるスウェーデンの奇才ロイ・アンダーソンが、時代も性別も年齢も異なる人々が織りなす悲喜劇を圧倒的映像美で描き、2019年・第76回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞(最優秀監督賞)を受賞した作品。この世に絶望し信じるものを失った牧師、戦禍に見舞われた街を上空から眺めるカップル、これから愛に出会う青年、陽気な音楽にあわせて踊る若者……。アンダーソン監督が構図・色彩・美術など細部に至るまで徹底的にこだわり抜き、全33シーンをワンシーンワンカットで撮影。「千夜一夜物語」の語り手シェヘラザードを思わせるナレーションに乗せ、悲しみと喜びを繰り返してきた不器用で愛おしい人類の姿を万華鏡のように映し出す。
引用:映画.com
出典:このブログに使用した映画の画像はすべて映画.comの出典です。
33シーンが繋がっているわけでもなく、
そのワンシーンに特別なモノがあるわけでもない。
あるのは映画的にデフォルメされた人々の
悲しみや怒り、悩み、幸せ、夢などの日常。
そういったシーンから見える心や脳内を絵画的に映像にしている。

この映画には何か物語、ストーリーを見つけようとすると、
がっかりするんじゃないかな。
あくまでも美術館へ行って、
「ロイ・アンダーソン展」を鑑賞するという気持ちで観ることをお薦めします。
絵画イメージで鑑賞すると
似ている絵画のイメージとしては
ファーストシーンはシャガールでしょうね。

早朝の朝のような空を二人の男女が飛んでくるんです。(戦禍の街だそうです)
パッと思いついたのはシャガールですね。
(予告でもシャガールの名前は出ていましたが。)

その次に映されたのが、このシーンですが
ご夫婦?が遠く空を眺めている。少し姿勢が不自然ですが。

このシーンでイメージできる絵画は
アンドリュー・ワイエスでしょうか。
なにか、吸い込まれていきそうなワンシーンを描いている絵に
とても似ている気がしました。

如何でしょうか。何となく似ている気がするのですが。
こんな対比もしてみると、また鑑賞の仕方が変わってくるかもしれません。
最後に
「ホモ・サピエンスの涙」のタイトルに戻ると
この映画のテーマが何なのかがわかるような気がする。
真っ直ぐに考えると「動物としての人間の涙」ってことじゃないでしょうか。
いくつかのシーンでこの涙を観たような気がします。

この世に絶望し、信じるものを失った牧師。戦禍に見舞われた街を上空から眺めるカップル…悲しみは永遠のように感じられるが、長くは続かない。これから愛に出会う青年。陽気な音楽にあわせて踊るティーンエイジャー…幸せはほんの一瞬でも、永遠に心に残り続ける―。人類には愛がある、希望がある。だから、悲劇に負けずに生きていける。悲しみと喜びを繰り返してきた不器用で愛おしい人類の姿を万華鏡のように映したアンダーソン監督渾身の傑作が、遂に日本に上陸する!
涙が流れていなくても、心の中で泣いていたり、頭の中では涙が流れていたり。
このタイトルに戻った時に、この映画の意味がわかったような気がしました。


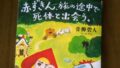
コメント